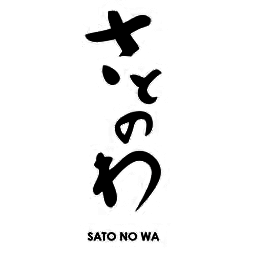去年、一昨年、東京で注連縄作りのWSを行いました。
指南役をお願いしたのは宮城県北、栗原市で地域資源、文化を
現代の視点も加えながら伝える「くりはらツーリズムネットワーク」さん。
ご参加へはキャンセル待ちをいただくくらいご予約をいただき、あらためて
『手作り』への”熱”を感じたひとときでした。
今年こそは自分たちでも作りたい・・・・という思いで挑戦することに。
勉強のために地域内で動き始めると、『縄を綯う』という事が、もはや
なんと消えゆこうとすることなのかをまざまざと知りました。
昔はどこの家でも手作りされていた縄、俵、草鞋や蓑、
田んぼ(米作り)をやっていることの象徴でもありました。
時は流れ、ライフスタイルも変わり、草履も蓑も俵も使わなくなり、おまけに
米作りも減少の一途(というか米余り対策の減反政策で)、
今はもうどこの農家さんでも縄綯いはしていません。(・・・ふぅ・・・)
お正月のしめ飾りも量販店で外国製を安く買うのが常です。
春から始まった毎月の里山カフェ、夏のメニュー、茄子漬けを作れるようになったのは
嬉しかったなぁ。だから(?)毎年指をくわえてベテラン母さんがつくるのを見ていた
「キュウリの古漬け」にも思い切って挑戦することにしました(笑)
日本の風土に根付いて脈々と伝わる暮らしや慣習や文化に無性に惹かれます。
なんでだろう?
理由はわかりません(笑)
でも、手間がかかり、面倒だけれど、なぜだか伝わるものがある「手作り」
というものに惹かれつづけて早5年余り。
稲わらとの格闘(?)を始めてみることにしました。
写真は鬼首・注連縄保存会の皆様が綯う神社のための注連縄。
この地区では、代々、稲わらではなく「菅(スゲ)」で綯ってきました、準備は6月
からはじまるのだそう。刈った菅を乾燥させ、保管、綯う直前の絶妙な湿らせ具合が
ポイントなのだそうです。荒雄川神社、鳴子温泉神社・・などなど、
鳴子の神様を奉る大事な神社に奉納される注連縄が、初お目見えさせる秋祭りまでに
急ピッチで綯われていました。
さあ、私も頑張るぞ(笑)